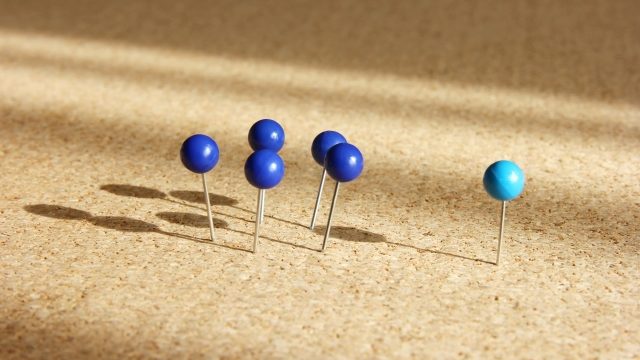吹奏楽部に入ろう!と決めたら次は希望する楽器を決めなくてはいけませんよね。
例えばトランペットかホルンがいいなぁ・・・と考えた時、どっちが難しいんだろう?と考えます。
吹奏楽部は厳しいって聞くからできるだけ難易度の低い楽器が良いなと思う人、音楽が得意だから難易度の高い楽器に挑戦してみようと思う人。
色々だとは思います。
ですが吹奏楽部の楽器に難易度は無いんです。
もっと細かく言うと、楽器の難易度は個人個人で違ってきます。
うちの子も同じようなことを入部前に悩んでいましたので、吹奏楽部の楽器の難易度と楽器決めについて書いてみようと思います。
Contents
吹奏楽部の楽器に難易度はない
吹奏楽部の楽器に難易度というものはありません。
ギネスブックには、金管楽器ではホルンが、木管楽器ではオーボエが一番難しいと書かれています。
たしかに楽器が上手に吹けることを前提にすると、ホルンはいろいろ技術がいるし、オーボエはリードによってうまい下手が決まるため、難易度が高いと言えるかもしれません。
でも吹奏楽初心者にこの理屈はあっていないんです。
だって、どれも吹いたことがないからどれでも同じくらいの難しさだからです。
口の形で難易度が決まる
吹奏楽の楽器は、楽器を吹くための口の形が決まっています。
口の形はアンブッシャ―と言いますが、口の形を吹ける形にしないと音が出ません。
アンブッシャ―の形に持って行きやすい口の形をしていれば、その楽器の難易度は低くなるし、アンブッシャ―を作りにくい口の形だと難易度は高くなります。
性格で難易度が決まる
また各楽器にはパートの役割がありますが、その役割が自分の性格にあっていないと、うまく合奏で音色を溶け込ますことができません。
なんでここで・・・とか、メロディー良いな~とか、メロディーばかりで緊張しすぎて消耗する・・・などのフラストレーションを抱えたままではうまく演奏できないんです。
もと精華女子高等学校の顧問をしていて、現在は活水高等学校の顧問をしている、強豪校を育てるカリスマ藤重先生は、楽器の変更をよくなさるそうです。
最初に決めた楽器が本当にあっているのか、自分の能力を発揮できるのはその楽器じゃないのかもしれない。
だから1つの楽器に固執しないようにいろんな楽器を吹かせてくれるそうです。
やはりいろいろ経験してみないと分からないのが楽器。
自分にとって難易度が高いのか低いのかを見極めてみないと分からないのです。
吹奏楽部の楽器 難易度をスマホに例えると
吹奏楽部の楽器の難易度は無いと言いましたが、スマホに例えると分かりやすいです。
iPhoneSEと、iPhone8、iPhoneXはどれが難易度が高いの?と聞かれて、答えられるでしょうか?
性能が良いのはiPhoneXだけど、iPhoneSEは古い機種にしては優れていて、大きさも小さいからポケットにも入れやすいんだよ。
学生ならSEで十分・・・
など、これはこうだけどこう、そっちはこうだけどこう、とそれぞれの特徴があって、好きなものを選んでいますよね。
最新機種がいい!という単純な理由で選んでいる人だっているはず。
それと同じで、吹奏楽部の楽器は楽器と言ってもすべて別物。
性能も違うし役割も違う。
スマホの機種のどれが自分が好きかと言うのは人それぞれですよね。
iPhoneが好きな人もいるし、androidのAQUOSとかが好きな人もいるし。
MacよりWindowsだ!という人は、いまだにアンチiPhoneを貫いているかもしれません(笑)
吹奏楽の楽器もそうなんです。
同じサックスでも「低い音がかっこいいから好き!」と、バリサクをやりたい人もいれば、「かっこよく高い音で吹きたい!」とアルトサックスを好む人もいる。
そして同じ楽器でもバリサクとアルトサックスでは口の形も息のいれ方も微妙に違います。
好きこそものの上手なれと言う言葉もある通り、その楽器が好きなら難易度云々よりもがんばればできるようになります。
楽器とはそういうものなんですね。
吹奏楽部の楽器 難易度よりもパート決めで重視されること
吹奏楽部の楽器決めは、各学校によって決め方が違います。
強豪校ではないところは、子どもたちが集まって話し合って決めることもあるかもしれません。
うちの子の吹奏楽部は、子どもたちが1つの部屋に集まって人気のない楽器から人数を埋めていったそうです。
トランペット、クラリネット、フルートは最後の最後。
それまでに「私譲ってもいいかな」と思った人たちが他の楽器へ流れていくようになっていました。
でも、強豪校では一度希望する楽器を吹いてみて先輩たちの投票で決めたり、先生と面接をして決めるなど、いろいろと方法があるようです。
吹いてみて決めると言われると上手下手で決まると思いがちですが、強豪校の先生は上手下手よりも別のところを見ているそうなんです。
体格
これはどこの学校でもあるかもしれませんが、体格の大きな子は大きな楽器になりやすいです。
とても背の小さな子がチューバやバスクラ、バリサクになると、手が届かない、足が床に付かないなどの問題が出てくるからです。
中学生の段階で背の高い子や体格のいい子は、低音楽器になりやすい傾向が全国的にあります。
性格
強豪校では、その子その子の性格を見て楽器を決めているそうです。
性格を見ると言うと、どんな子がクラリネットになるの?と考えがちですがそうではありません。
1人ずつ吹くときや面談を通して「将来この子はパートリーダーやセクションリーダーとして役割を果たしてくれそうだな」という子を何人か先生が選びます。
そしてその子たちが1人ずつ各パートに入るように配分するんです。
メンバー構成
将来のパートリーダー候補を決めたら、その子たちの楽器をあらかじめ決めます。
そしてそのパートに配属する子たちが、そのパートリーダーと気の合いそうな子を選んでいきます。
あまりに気が合わないとケンカしちゃいますもんね。
また現在のパートの雰囲気もみながら入れていくようです。
そのうえで、希望する楽器と楽器を吹いたときの上手下手も見るのかもしれません。
楽器を吹いたとき、ベテランの先生なら「この子はこの楽器よりもあっちの方が向いてるな」と分かるそう。
ですから、楽器決めは私たちが思うよりも組織づくりの一環として顧問の先生は考えているようですよ。
楽器は練習すればおのずと上手になるもの。
実際、プロの演奏家でも中学、高校とは違う楽器でプロになっている人もたくさんいるんですよ。
それだけ、本当に合う楽器選びと言うのは難しいと言うことなんですね。
この記事では吹奏楽部の楽器に難易度は無いことについてお伝えしてきました。
楽器に難易度は無いというとちょっと語弊があるのかもしれません。
楽器の難易度には個人差がある、ということなんですね。
うちの子も初めはフルートを希望していましたがクラリネットになりました。
でも結果的にはクラリネットで良かったと言っています。
たまにお友達にフルートを吹かせてもらうこともあるそうですが、どっちが難しい?って聞かれると答えるのが難しいと言います。
だってクラリネットとフルートでは口の形が全然違うから。
あとはクラリネットの方がメロディーが多いから結果としては良かった気がする、と言っていますし、フルートの子は自分だけが吹く旋律が多くて嬉しいと言います。
それぞれの楽器は比べることのできない、全くの別ものなんですね。
このご時世、お買い物に行くのも大変ですよね。
楽器関連で必要なものは島村楽器がおすすめです。
品ぞろえも良いですし、楽器が欲しい時も店員さんが試し吹きをして良いものを選んでもらえます。
また最近話題になっているサックス用のゴッツ(Gottsu)”サイレント リード”(Silent Reed)も島村楽器では扱っているんですよ。
|
|
他にも「こんなものあったんだ!」とびっくりするようなものが沢山あるので、見てみてくださいね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2029579b.725b2cca.2029579c.8d2606e1/?me_id=1197372&item_id=10010131&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwindbros%2Fcabinet%2F00894811%2Fimgrc0079653000.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)